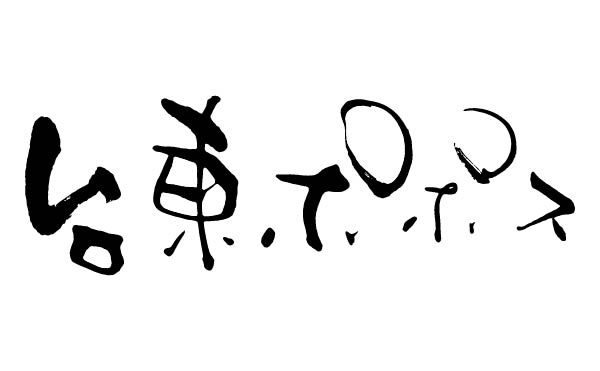コーヒー「だい吾」も開店から1年半を過ぎたのだそうです。
はや5便を数えるまでになった「だい吾便り」。今回は以前にお寄せいただいた珈琲が「動き出した」迷いの先のお話しでしょうか。「芸術」「食欲」「読書」「スポーツ」――秋を彩る言葉はたくさんありますが、珈琲もまた、とりわけこの季節に良い。そんな気持ちになるお便りを頂戴しました。
だい吾便り⑤ ~美味しいの先へ~
閉じていくものと開いていくものと、その違いは何だろうか。やがて終わるものと、どこまでも続いていくものは、何が違うのだろうか。終着点としての結果か通過点としての結果か、どちらかを選べるものなら、私は途上のものを選びたい。私は終わらないもの、ずっと続いていくものを求める。
こんなことを思いました
毎日、毎日、飽きもせず珈琲の美味しさを追求している、そんな姿は傍から見れば、少し風変りに見えるかもしれません。
一年程前の頃は「美味しい」という一つの点、結果に向かって自身の珈琲を進めていたように思います。大切だったものは「美味しい」という結果、自身の珈琲が以前と比べて「美味しく」なったことで、そこに至るまでの過程の部分はあまり意識していなかったように思います。
とにかく美味しくなければいけない、客観的に見ても至らない部分がある、そんな気持ちで珈琲に取り組んでいました。この時、過程――点に至るまでの線――はそれ程、意識していなかったように思います。
もう少し時間が経って、珈琲を召し上がって下さるお客様から「美味しい」と言っていただけるようになった頃、私は何か物足りなさを感じていました。確かに作った本人が飲んでも「美味しい」と思えるものになっているが、どこか退屈な、一口飲んで分かりきってしまう「美味しさ」になっているとも感じました。美味しさは、(点は、)その動きを止めているようでした。

美味しいという点だけを求めていく中で、点は小さな枠に収まっていったように思います。枠の中に収まったものは「美味しい」には違いないのでしょうが、一面的な美味しさに留まっており、「美味しい」の先に進めなくなっていました。
そんな、美味しさの先とは、一体どのようなものなのでしょうか。作った側から、あるいは作ろうと思った時には、その美味しさが予想出来てしまうものではなく、作った本人でさえもどこか分からない部分がある「美味しさ」、形が定まりきっていない「美味しさ」ではないかと思います。
珈琲が「美味しい」だけに留まらず、その内にある未定形の部分が、さらに次の「美味しい」につながっていく感覚。結果に至るまでの過程があるからこそ、さらに次の結果をイメージ出来、次なる過程を伸ばしていける、そんな連続。
「美味しい」というだけの結果は、はたしてどれ程の意味を為すものなのでしょうか。結果だけを求める姿勢では絶対的な停滞を招き、しかしそれが過程を意識した結果であるならば、結果はどこまでも自然に動いてくれるように思います。
私が珈琲を動かすのではなく、珈琲自らが一人勝手に動き回り、その後をトボトボと追いかけていく私。そんな風に行き先も分からずに進んでいく力を信じています。
今回は、こちらで失礼致します。
2025年11月吉日
内田大吾