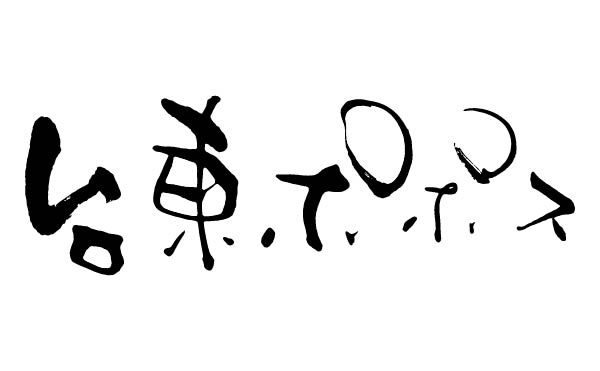根津で二十年余、界隈で幾度かの移転を経ながら愛され続ける酒場「たまゆら」。
バーのようでいてバーでなく、スナックではなくクラブでもない。
店主様は「一期一会のサロンみたいなものだといいわね」とおっしゃいます。
ご好評頂いております「たまゆら便り」。 前回のご寄稿からなんと1年が経過しておりました。
この間に幾度か、本稿をお読みになられた皆様からのお声を聞く機会があったことなどもあり、そんなに時間が空いていたことを私もすっかり失念しておりました。
17便では、久し振りに来訪されたお客様とのお話から、異郷の空、心の中にある空へと広がるお便りをお寄せいただきました。
たまゆら便り⑯ ~松本の空、五月の空~
或る若者から、久し振りに東京へ出向く由とその日のたまゆらの営業への問いが有りました。メールを拝見の際、どうやら「お変わり無いでしょうか」の文面から見てしまい、その前に認めて下さっておられる件りを失念してしまい、お会いして其の旨を口にされた時、初めて気付きビックリ致しました。
思うに暫く寄稿せずにおいた月日の私を案じてのお変わり無いでしょうか、だったのだと、大分経ってから気付いた粗忽者です。
彼が久し振りにドアをくぐって下さった夜、今まで以上に沢山の話しを伺いました。
今は以前の職場と違って京都でのお仕事をされているとか、その職をもこれから京へ帰り10日を待たずに辞め、郷里へ帰られる計画だとか。お会いせずにいた歳月の中での彼の経過と変化、成長を実感させて頂く事になる会話でした。

彼の故郷は長野松本市であるようです。
10年近く前、友人と飛騨高山経由で古川へ行く時に、彼女の提案で高山まで高速バスに揺られた日に、確か松本を経て高山へ入ったので、その素通り体験以外かの著名な松本を露とも知らない私でしたが、俄然興味が湧きました。好青年の彼が一番の良き年令を迎え、以後郷里でと思われた事で、断トツに松本に惹かされました。
彼は帰省した後、スイカ農園で汗を流される選択をされました。
スイカ?私には余りにも唐突で未知の言葉に思えてしまい調べて仕舞いました。
諸説有る中で、おおよそ熱帯アフリカ砂漠地帯が原産とされ、原初果肉は今ほどの甘さは無く、種を食べていたようです。
其の後、地中海を越えヨーロッパ南部へと入り、今日のように果実を食べる食物へと発達を遂げたようです。先人は、すいかの種には脂肪や蛋白質が豊富に含まれ、解熱効果がある事も知っていたようです。ツタンカーメンの墳墓等4,000年以上前の遺跡から種が発見されていて、壁画にはいわゆる楕円形のすいかが描かれているそうです。425年頃のイスラエルのモザイク画にもオレンジ系の色のすいかの果肉が描かれているとの事です。
食品種改良に関しては、素朴に日本が唯一無二くらいに思っておりましたが、いえいえ、様々な国で人々が品種改良を重ねて現在に至っているのですね。
日本へは、中国の西方(シーグァ)から中央アジアの瓜として入り、西瓜となったとの事。鳥獣人物戯画にはウサギが縞模様の作物を運んでいる図があるとの事です。
江戸時代の農業百科事典には、大胆なすいかの図が載っています。昭和に入りつる割病対策として、抵抗性を持つカボチャの台木をあて接ぐ方法を開発し、他の野菜への接ぎ木をも発達させていったようです。野菜果物も一生懸命な大勢の専門家がおられるのですね。

彼は、これからの幾つかの未来図を話して下さり、「漁業を復活させようと思っています」と言う。松本で漁業? と思いきや、河川での仕事も確かに漁業であります。
彼のご祖父の時代、にじます等盛んに漁業を営む方々がいらしたとの事。その河川も今や藻類が蔓延り、漁業のなごりも無きに等しい様相を呈しているのだそうです。
彼はそれを一人からでも出発し、漁業を再び松本のものとしたいと生き生きと語りました。
彼のご両親は学校時代の同級生同志のご夫婦だそうです。そう云えば、以前大変にお世話になったお客様ご夫婦も再婚同志のカップルで、松本生まれの同級生同志と伺いました。
松本とは、そうした青春時代を過ごすに、そして離れて尚戻る選択をし得る気持の良い地なのかもしれません。
それにも増して、生れた地を離れ他地で様々な体験をしながら、人の言う当り前に流されず、自分の力で学び、自分の力で考え、しっかりとした思考力を身につけた彼が選択した自らの道なのでしょうと思います。
「僕の後に続く若者が多くいることを信じています。」と彼は清々しく帰って行きました。標高度500~600mの高原地のすがすがしい空を想います。

不意と、行き倒れ渋沢栄一の興した養育院で死んだ絵画きを評した寺田透の言葉が浮かびます。
――野卑で猥雑な環境の中に生きた長谷川の絵は、そのモデル達に対しても形や色のつけ方の点で、何の美化の努力も払われていないにもかゝわらず、総体として汚れがなく、ほのぼのと歌うような印象さえ、われわれの記憶のうちに残す不思議さを持っている――
今年は久し振りに小石川植物園を楽しみたいと思います。そこに一重の薔薇花のような桜花の群れ咲く樹が在るのです。
植物園から広がる大きな空は、松本へも繋がっています。
「塵芥の中に坐するのが清涼です。聖女もバイタも私です。」
長い苦悶からあけ、二十歳そこそこの生娘だった私の脳裡から産まれ出た言葉。そして、その五月の蒼い空を思い出しています。
2025年3月吉日
たまゆら拝